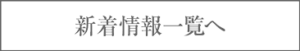「大河」の愛称で親しまれているNHKの大河ドラマ。テレビ離れが加速して、視聴率自体は低迷しているといわれますが、着物ファンの中にはご覧になっている方も多いのではないでしょうか?最近では、当日の視聴率は低くても、ネットの情報などをチェックしながら観たい放送回だけを見逃し配信で観るとか、タイパ優先とばかりに見逃し配信や録画データを倍速で観るなど、昭和の時代にお茶の間に家族が集まって大河ドラマを観たのとはひと味もふた味も違った新しい楽しみ方もあるようです。
さて、今年の大河ドラマはご存知「べらぼう」で、若い役者さんたちの活躍をベテラン勢がしっかり脇で固めるという豪華で盤石なキャスティング。着物ファンとしてはやっぱり気になるのは衣装や、歌舞伎にも描かれる吉原の花魁でしょうか。話は少し逸れますが、花魁といえば、歌舞伎の「六助由縁江戸桜(ろくすけゆかりのえどざくら)」に登場する三浦屋の揚巻の美しさは圧巻です。特に坂東玉三郎丈の揚巻にはもう息を飲み、瞬きを忘れるほどです。ちなみに、お弁当屋さんやコンビニなどで売っている「助六」というあのお寿司セットの由来がこの花魁の揚巻です。「揚」がお稲荷さんで「巻」が海苔巻きというシャレでそう呼ばれるようになりました。こうしたシャレが効いているのがまさに江戸の粋なのです。
もちろん衣服も、贅沢が禁じられれば表は地味でも裏地にはシャレが効いた文様や、口には出せないお上の批判を描いたものを取り入れたり、大根とおろし金を描いて「だいこんおろし」とばかりに大根役者を舞台から降ろそうと思ったりと、まぁ~面白いこと枚挙にいとまがありません。
腹が立つほど暑い夏は、今年の大河ドラマ「べらぼう」の衣装や着こなしをお手本に、シャレの効いたコーディネートを工夫してご自分なりに遊んでみてはいかがでしょうか?ちなみに衣装デザインはファッションクリエーターの伊藤佐智子さんが担当しています。浮世絵を参考に着物や帯はもとより半衿や小物といった細かいところまでデザイン、スタイリングしているそうです。浮世絵では衿をキッチリと合わせている姿ではなく、グズッとしているものばかり。その辺りの着こなしにも配慮されていると聞けばますます興味は募ります。
着物ファンの皆さまには、ご存知の方も多いと思いますが、明治時代に化学染料が外国からもたらされるまでは、衣類のあらゆる「色」は天然染料でした。いわゆる植物染め(草木染め)です。そして、目に入るほとんどの葉っぱは緑色なのに、緑色の染料は存在しないというこの不思議。そんなわけで、伊藤佐智子さんいわく、べらぼうの主人公、横浜流星さん演じる蔦重の衣装をデザインするときに、単なる藍染ではなく緑色に決めた理由を「何者でもない彼が何にも縛られず、やんちゃで発想豊かに、新しいものを生み出していく。そんなオリジナリティーあふれる人生のスタートを象徴する色として、たやすく再現できない緑という色を選びました」とNHKのサイトに書いてありました。さぁ、この後どのような展開になるのか、衣装やシャレも同時に最後まで楽しみたいところです。