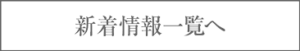〇水源の森の工場
京都市北区・釈迦谷に本社を構える、老舗帯メーカー「おび弘」さん。その美しい庭をお借りして撮影を行った折、制作の現場も見せていただけることになりました。工場は琵琶湖の北にあるとのことで、京都市内から車で向かったのですが、思っていたよりも道のりは長く、有名なメタセコイヤの並木道を抜けて、ようやくたどり着いたのは、自然豊かな山門水源の森の中でした。
迎えてくださったのは、「おび弘」三代目の池口寧祥社長。なぜこの場所に工場を構えているのか、お話を伺うと、
「景気の良い時代には、四カ所の工場があったんですよ。福井県の高浜にもありました~、でも今はここ一軒だけにしました。機は30台ありますけれど、今織っているのは7名だけになりました。5年前まで13人いたんですけれど、だんだんこの技術を伝承していけるのかどうかの瀬戸際になってきています。もともとは、自宅で機を織るいわゆる「出機」の人がいたり、このあたり出身の女性が多くて、出稼ぎで京都へ来て機織りをして、実家は帰っても農業しかすることがないので、ここに工場を作ってくれという要望も多かったんです。このあたり、山門地区は昔から「水源の森」と呼ばれていて絹織物に適した美しい水と、十分な湿度があったのでちょうど良かったのです。
〇手織り帯を100年先に残したい
おび弘さんでは、綴れ、錦、緞子、絽綴れ、羅、紗など多種多様の帯を織る高い技術を持っています。また、おび弘と名前を出さずに帯メーカーさんや問屋さんの伏せ機(オリジナルの留め柄)も織っていましたが、注文はだんだんと減っているそうです。
「本袋を織ろうとなると1ヶ月じゃ織り上がらないんです。2ヵ月はかかることを思うと良し悪しなんですが、しかし、機械では織れないものを残していきたいんです。
錦と綴れを同時に織るなんていうのは、やっぱり手織りじゃないとできないんですよ。手の技術を残していきたいというのが今、一番の思いです。もちろんたくさんは織れませんが、逆に誂えでも1本だけ織ってくれるという注文にはどんなものにでも対応できるので、そういう注文も増えてきました」と池口さん。
そう言いつつも、職人さんはあと7人を残すのみ。手でした織れない羅などは年配になって視力も落ちてくるとなかなか織りにくい時代になってきたと、日本の伝統技術が消えていくことを危惧している様子でした。
最後は少ししんみりしてしまいましたが、それでも、手織りならではの美しく、しなやかな地風で締めやすい帯を、どうにかして残してもらいたいという思いを胸に抱きしめて、暮れなずむ琵琶湖沿いを眺めながら帰路につきました。
※「るると」より要約引用