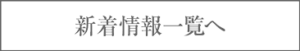こんにちは、佐沼屋です。
後編の今回は、佐沼屋の着方教室について、前編よりさらに具体的に講師の洋子常務にお話を伺いました。
特に今回は、教室で指導している「前結び」について、詳しく掘り下げてご紹介していきます。初心者の方にもわかりやすく、実際にどのような方法で学べるのか、また前結びの魅力やバリエーション、後ろ結びとの違いなどについても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
〇佐沼屋で習う帯の「前結び」について
佐沼屋の着方教室では、帯は「前結び」で習います。前結びとは、帯を体の前で結んで形を整えてから、結び目ごと後ろへ回す方法です。
この方法の大きな魅力は、鏡を見ながら結び方を確認できることにあります。たとえば、お太鼓の大きさを調整したり、柄の位置を合わせたりといった作業が視覚的に確認できるため、初心者の方でも形が作りやすくなります。帯を前で完成させてから後ろに回すだけなので、後ろに手を回して結ぶ必要がなく、慣れていない方でも無理なくきれいに結ぶことができるのもポイントです。
実際に、初めて着付を習う方や、着物を日常的に楽しみたい方の多くに前結びは取り入れられています。自分で着物を着られるようになる喜びを感じやすいという点で、前結びはとても優れて方法だと言えるでしょう。
一方で、「後ろ結び」が劣っているというわけではありません。後ろ結びは、帯を背中側で直接結ぶ伝統的な結び方であり、現在も多くの着付教室やプロの現場で主流となっている方法です。
ただし、後ろ結びは手元が見えず、“手探り”の状態で形を作ることになるため、初心者には難易度が高いという面があります。特に、帯の形を確認しながら結ぶことができないため、最初にうちは仕上がりのバランスがとりづらく、慣れるまでに時間がかかることもあります。
そのため、後ろ結びは正式な着物の着付を学びたい方や、伝統的な作法を身に着けたい方向けの教室に多く採用されています。プロの着付師を目指す方や、舞台や式典などで正装に対応したいという方には、後ろ結びの技術が求められることが多いです。
近年では、前結びを教える教室も増えており、初心者向け・実用向けの着付け方法として注目を集めています。特に「自分で着物を着られるようになりたい」「日常的に着物を楽しみたい」といった目的を持つ方には、前結びがぴったりです。短期間で着られるようになりたいというニーズにも応えやすいため、目的に合わせて結び方を選ぶことが大切です。
〇前結びの種類について
「前結び=お太鼓だけ」と思われがちですが、実は前結びでも様々な帯結びが可能です。
代表的な「お太鼓結び」は、結婚式や式典などの正式な場でも使える格式高い結び方で、着付けの基本ともいえる形です。また、お太鼓を二重に重ねる「二重太鼓結び」は、より華やかで安定感のある仕上がりになります。こちらはお太鼓よりもややボリュームがあり、重厚感を出したいときに向いています。
それ以外にも、たとえば:
・ふくら雀:丸みのある可愛らしい形で、訪問着などに合わせても華やかです。
・文庫結び:シンプルでやわらかい印象を与える結び方。帯幅が狭い場合にも向いています。
・貝の口結び:簡単に結べて、カジュアルな装いによく合う形です。
・平結び(平帯結び):帯を平たく折り重ねて結ぶ方法で、すっきりとした軽やかな印象に仕上がります。
これらの結び方も、前結びで行うことができます。鏡を見ながら結ぶことができる前結びだからこそ、アレンジの幅が広がり、発想も柔軟になります。佐沼屋の着方教室では、そういったアレンジの楽しさも学びながら、自由に着物と向き合える時間を大切にしています。
また、前結びはすでに他の流派で後ろ結びを習った経験のある方にとっても理解しやすい方法です。後ろ結びの動作を経験しているからこそ、前結びを学ぶことで「この手順は省略できるんだ」「こうするともっと簡単にできる」といった新しい発見があります。
実際に、以前は後ろ結びをしていた佐沼屋の社員も、洋子常務が前結びの資格を取得して教えたところ皆がおよそ1週間程度で前結びをマスターできました。
〇洋子常務から、着物を着てみたいと思っている初心者の方へ
「着物を着てみたい」という気持ちがある方なら、誰でもきっと楽しめると思います。
ただし、“ただ料金が安いから行ってみよう”という気持ちでは、中々身に付かない印象があります。
たとえば以前、佐沼屋のお客様で、お嬢様が香港で結婚式を挙げられるという方がいらっしゃいました。その方は「どうしても現地で着物を着たい」という思いから、夏用の着物をご用意されて7日間ほど佐沼屋の着方教室に通い、一生懸命練習してご自分で着られるようになりました。
このように、「この着物を自分で着たい」という強い思いがあると、やはり上達のスピードも全く違います。“もったいないからこの古い着物で練習しよう”というよりも、“この着物でお出掛けしたい”という気持ちを持って練習する方が学びの効果は高いと感じています。
〇最後に
着物を楽しむうえで基本をきちんと身に付けることは大切ですが、形式に縛られ過ぎることなく、覚えた基本を活かして自分らしくアレンジを楽しんでいただきたいというのが洋子常務の考えです。
また、「着物でお出掛けする前に復習したいのですが、見てもらえますか?」というお問合せも実際に頂くことがあります。その場合は、一度教室(全6回)を受講して頂いた方であれば、次の練習日以降の午後の時間帯に予約を入れて頂くことで、洋子常務が着付けのチェックを行うことも可能です。
自分で着物を着る楽しさを、ぜひ佐沼屋の着方教室で体感してみてください。