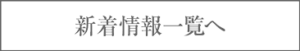ときには、たんすの中の着物や帯を引っ張り出して、あれこれと組合せを試してみるのも楽しいひととき。着物の上で帯をのせて眺めていると、思いがけず新しいコーディネートがひらめくこともあります。そんな時間は、着物好きにとってはちょっとした研究タイム。ついでに半日ほど風を通して虫干ししたり、気になる汚れやカビの早期発見にもつながれば、一石二鳥です。春先の湿度が低いうちに、そんなお手入れも兼ねて楽しんでみてはいかがでしょうか?
ところで、ここでは帯のことを少しだけ深堀りしてみようと思います。そもそも「おび」という言葉の語源はどんなところにあるのでしょうか?その語源は「お=緒」(細い紐)+「び=結び」あるいは「佩(お)ぶ」(身に着ける)からきたという説もあります。
さて、「帯」という字を使っていくつ単語を書けますか?テレビのクイズ番組のように、ちょっとここまで読んで挑戦していただけたら楽しめると思います。「包帯」「帯刀」「帯同」「温帯」「世帯」「携帯」「所帯」「地帯」と多様な意味を持つ帯は、意外と私たちの日常生活に深く溶け込んでいることが良くわかります。もうひとつ面白いのは、着付けの道具に帯と付くものが異様に多いため、着付け教室の先生が「帯板を持ってください」というと、必ずお1人くらい別の物を持っていたりするという話を聞いたことがあります。「帯枕」「帯締」「帯板」「帯揚」と、ずいぶん帯が付く小物が多くあります。また、「帯祝い」「帯占い」など道具以外にもありますね。
帯は、日本人の、最も古いとされる衣服「貫頭衣」に結んだ紐からスタートしています。呉の国から衣服が伝わり衿を合わせて着用するようになると徐々にきらびやかな衣装になり、帯も装飾的な役割を持つようになりました。これが今の帯の原型と言えるでしょう。その後も帯は時代によって衿を合わせて脱げないようにする役割と同時に、装飾的な意味合いはどんどん強くなっていきます。
時は流れて武家社会の小袖スタイルが町人にも広まっていくと、今の着物の形に近づいていきます。江戸時代の前期には二寸(7.5cm)ほどだった帯は、段々幅が広くなり、天下泰平の世になると文化が栄えるにつれて髪型も帯も豪華になっていきました。
江戸末期には、亀戸天神の太鼓橋が再建された際に、深川芸者衆が太鼓橋を模して結んだのがおしゃれだと、一気に広まりました。これが現在のお太鼓結びの原型で、帯揚、帯締、帯枕などが今と同じような使い方になっていきます。
重く、結ぶのが大変だった丸帯。男衆(おとこし)たちに着せてもらう芸妓さんたちプロは良いのですが、自分で結ぶのはあまりに大変だと「袋帯」が生まれたのは明治中期、女性の社会進出と共に名古屋の女学校の先生が考案したのが「なごや帯」と、時代の変遷と共に、帯どのものも、結び方も変化をしてきました。着物ファンの皆さんも、ご自分の個性に合った帯を選び、個性を表現するための帯結びを研究してみてはいかがでしょうか?