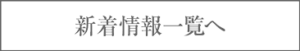〇着物だけにとらわれない作品づくり
12月のある晴れた日、東京駅の慌ただしい空気のなかを抜け、ある工房へと向かいました。訪ねたのは、十一代目岩井半四郎の舞台衣装なども数多く手がけている、東京友禅作家・大嶋進氏の自宅兼工房です。
高速道路から中央道へと進み、一般道へ入ると、沿道の景色が少しずつ変わっていきます。常緑樹の間に、葉を落とし春を待つ並木の枝が交じるようになり、どこか静けさとあたたかみを感じさせる風景が広がっていました。車の窓越しに武蔵野の空を見上げていると、せわしなかった気持ちがだんだんと和らいでいくような心持ちになりました。閑静な住宅街に入ると静寂が増し、路地の突き当りに「染芸 大嶋工房」はありました。
玄関先で迎えてくださったのは奥さま。衿を正してぞろぞろと暖房の効いたリビングに誘われると大嶋氏が気さくな笑顔で待っていてくれました。挨拶をし、名刺交換をしたあと、奥さまが丁寧に出してくださった美味しいお茶や珍しいフルーツ大福に雑談がはずみ、親戚の家を訪ねたかのようにすっかりくつろいでしまいました。楽しく笑っているうちに取材を忘れてしまいそうな一同に、大福を食べ終わった頃を見計らったように大嶋氏が天井を指して、
「さぁ、それでは上の仕事場へ…」と立ち上がります。途中の和室の前で「ちょっとご覧になりますか?」と誘われました。そこには50号もの大きな作品がドーンと飾られていました。「朝霧」というタイトルのその作品はそのまま景色の中へ入って奥まで歩いて行きたくなるようなモノクロームの濃淡世界。その反対側には鷲が描かれた大きな屏風。いずれも壮大な作品で、日本画なのかと見まがうような独特の迫力がありました。
実は、大島氏の活動は着物だけにとどまらないのです。上村松園の孫で、京都市立芸術大学名誉教授で文化功労者の上村淳之氏の原画を、蠟染めで六十面の襖絵に制作し、特別公開されたのは2018年秋のことでした。奈良の當麻寺奥院の重要文化財の大方丈六室の六十面に渡る襖絵「花鳥浄土」を、上村氏の監修すべて白山紬の地に染め上げたというのです。襖絵は当然のことながら和紙に日本画が描かれることが一般的ですが、世界的にも初という染めによる襖絵が誕生しました。
〇徐々に物のカタチというものが分かってきた
大嶋進氏は長野県伊那市の出身。
「中学校卒業までは向こうにいたんですが、もう東京へ出てきてからのほうが長くなりましたね。当時は集団就職が多い時代でね、手に職を付けるようにと親にも言われて、東京で学校出してやるって言われて…」と、淡々と生い立ちを話してくれました。親戚が東京で着物の加工をやっていた関係で縁があって住み込みで目黒にあった工房で働く生活がスタートしました。最初のお給料は500円程度だったと述懐します。
朝起きると先輩たちの筆洗の水くみから始まる一日。洗い物と、準備後片付けは大嶋氏の仕事になりました。同郷の先輩がいたことも心強く、反物を担いで高田馬場までのお使いに行ったり、休みの日は映画を観たり、植物園でスケッチをしたりという淡々とした日々が続きました。
「世間のことなんて知らないから、とにかく真面目にやるしかなくてね。先生からは、とにかく絵心だ!と言われたけど…」という大嶋氏。もともと絵を描くのは好きだったせいか、スケッチをつづけているとだんだんと物のカタチというものが分かってきたといいます。
そのうち、後輩が入ってくると、徐々に部分的に先輩や先生の仕事を手伝わせてもらうようになり、覚えてはまた別のところを手伝って…、としているうちに、すっかり任せられる仕事も少しずつ増えてきました。
「普通の勤め(サラリーマン)だったら続かなかったかもしれないな~」と遠くを見るような表情で見上げた壁の向こうには、お孫さんたちの、幼い頃のあどけなくも生き生きとした一瞬の表情を切り取ってスケッチした、モノクロのデッサンがずらりと飾られていました。
そのお孫さんの七五三の衣装や、成人式の振袖はもちろん大嶋氏が一から全て一人で手がけたもので、そのプロセスや実物を見せてくださる時の表情は、作家でも職人でもなく、すてきなおじいちゃんの顔を垣間見せてくださいました。
仕事部屋には大きな窓から陽差しが注ぎ、大きなテーブルにはパソコンの最新モニターやプリンターが置かれ、横にはおしゃれなガラスのテーブルもあります。確かに図案を写し取るためにガラスのデスクを使う作家は多いものの、なんとなく想像をしていた友禅作家の仕事場とはどこかちょっと違う印象です。デジタルな設備に驚いていると、
「以前はね、卓球台の上で仕事をしていたんですよ~」といたずらっぽい笑顔で教えてくれました。聞けば卓球もなかなかの腕前だそうで、なんとも自由で、なにものにもとらわれない柔軟な発想に思わず聞いているほうも伸びやかな気持ちになり、自然と笑みがこぼれます。
〇考えている時間のほうが圧倒的に長い
技法についての説明を求めると、パソコンを起動し、大きなディスプレイに写真を写しながら、丁寧に、素人にも分かりやすいように一つずつ、時系列で丁寧に教えてくださいました。さながらWEB関係の技術者のプレゼンテーションのようなかっこよさ。おまけにすごくわかりやすくてうれしくなります。
十一代目岩井半四郎作品で見た作品は確かに東京友禅でしたが、大嶋氏の仕事はいわゆる糸目のある友禅染にとどまらず、ろうけつ染め、そしてたいていは外注してしまう引染めに至るまで、その技法の幅の広さに驚かされてしまいました。聞けば銀座の有名呉服店の店舗の中にある襖には、正真正銘、和紙に墨染めでグラデーションを描き出したこともあるのだとか、確かに卓球台くらい大きなテーブルが必要だったわけだと一同ここで納得。
「和紙は反物とにじみ方とか全然違っていてすごく大変だったんだけどね、できないって言うのはいやだから…」とぽつりとつぶやいた大嶋氏。ノーと言わないこと、あつらえや注文品を受けると、その要望を実現するために、よく考え、そのために創意工夫をこらしていくことで、使いこなす技法が増えていったのだろうと推察しました。一つ制作するごとに吸収してまた大きくなっていく。
「図案は、手描きでもパソコンでも色をいくらでも付けられるんですけど、墨が好きなんですよね。色を付けちゃうと発想が固定されちゃうから墨で描いてイメージを広げてくんです。僕は職人だから言われたこと(注文)と、自分がやってきた経験と、それを解釈して…折り合いをつうけていくんですね。いい加減な返事はできないし、自分で納得した物を作りたいという感覚が強いんですよね」
手を動かしている時間よりも、考えている時間のほうが圧倒的に長いという大嶋氏。考えなきゃいけないから即答はできない。そんな大嶋氏の仕事ぶりにほれ込んで、川中美幸さん、藤あや子さん、坂本冬美さん…と、枚挙にいとまがないほど多くの著名人が大嶋さんの工房のドアをたたきました。人間国宝十五代片岡任左衛門丈着用の衣装を手がけたことも。
できないと言わない気持ちの強さと柔軟で広い心、懐の深さでチャレンジを続けてきた大嶋氏は、どんなに雪が覆い被さっても、どんなに強い風が吹いても折れることのないしなやかで美しい青竹のような人でした。その技術の高さと懐の広さに惚れ込んだ十一代目岩井半四郎も、2001年から、この工房を訪ね共に物づくりをしてきました。一切の妥協をしない二人のラボレーション作品は、着て動いたときに美しいというコンセプトを守り続けています。
※「るると」より要約引用